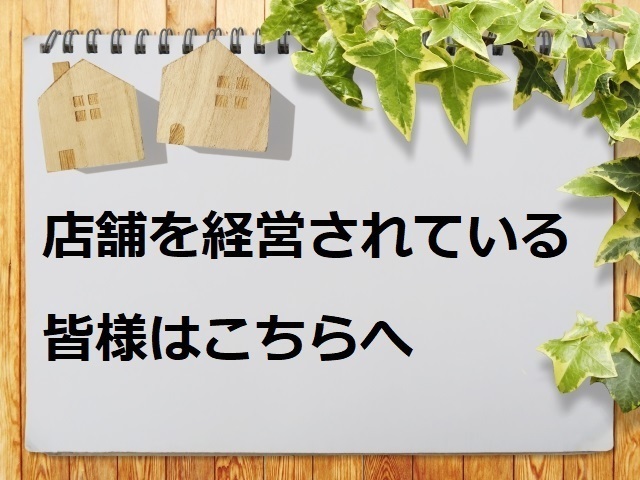東京都港区南麻布 藤岡公認会計士事務所・藤岡正光税理士事務所 中小企業の経営者を支える会計事務所
東京都港区白金3丁目5番11−202号cyuu
営業時間:9:00~18:00(土、日、祝祭日を除く)
創立費と開業費
会社設立後、まず最初に処理しなければならない項目として、創立費と開業費があります。どこまでの支出が創立費及び開業費とすることが出来るか。会計処理はどのようにすればよいか解説します。

創立費及び開業費とはなにか。
創立費とは、会社を設立するまでに要する特別な支出をいい、開業費とは、会社成立後事業を開始するにあたって開業準備に要する支出をいいます。
具体例として、会計上は財務諸表等規則ガイドラインに次のように掲げられています。
【創立費】
・定款及び諸規則作成のための費用
・株式募集その他のための広告費
・目論見書、株券等の印刷費
・創立事務所の賃借料
・設立事務に使用する使用人の手当給料等
・金融機関の取扱手数料
・金融商品取引業者の取扱手数料
・創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用
・発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額
・設立登記の登録税
【開業費】
会社成立後、営業開始までに支出した開業準備のための費用で、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等
また、法人税法施行令には次のように掲げられています。
【創立費】
発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの
【開業費】
法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
創立費については、会計上と税務上の範囲はほぼ一致していますが、創立事務所の賃借料や使用人の給与等は設立後も継続して発生する経常的な支出であるため、税務上の創立費には該当しません。
開業費については、会計上は、会社設立後営業開始までに支出した費用がすべて含まれるのに対して、税務上は開業準備のために特別に支出する費用だけに限定されています。
会計上の取扱い
繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用として、すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用(企業会計原則注解 注15)と定義されており、効果の及ぶ期間にわたって合理的に配分するものとされています。
すなわち、将来にわたって費用処理するために経過的に貸借対照表に計上したものにすぎません。
【創立費】
原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。
ただし、繰延資産に計上することもできます。繰延資産に計上した場合は、会社成立の時から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければなりません。
【開業費】
原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。
ただし、繰延資産に計上することもできます。繰延資産に計上した場合は、開業の時から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければなりません。
また、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができます。
開業準備は通常の営業活動ではないため、原則として営業外費用で処理しますが、営業活動と密接に関連する費用であることから、販売費及び一般管理費で処理することも容認しています。
税務上の取扱い
創立費及び開業費について、それぞれ任意に費用処理することができます。
つまり、
① 会社設立時又は開業時に全額費用処理
② 全額資産計上したままとする
③ 計上した繰延資産のうち、一部を費用処理する
④ 資産計上した場合の会計上と同様に5年以内の一定期間にわたり定額法により償却
を選択できることとなります。
すなわち、任意に費用処理することができるということは、例えば創業期は課税所得がマイナスなので②の選択をし、課税所得がプラス転換した期に、③の費用処理することによって節税を図ることができます。
ただし、課税所得がマイナスの期に費用処理したとしても、税務上の繰越欠損金として、将来の課税所得がプラスの期に課税所得から控除することができますので、通算すると税負担は変わりません。
なお、欠損金の繰越控除ができる条件がありますし、会社設立時には青色申告の承認申請は忘れずに必ずしておきましょう。
また、税率が変更になると課税所得がいつ発生するかによって税負担額が変わってきますので、税のシュミレーションをしっかり行いましょう。
実務上の留意点
会社設立前に必要な費用について、発起人などが個人として支払う場合もあります。社長1人の場合は、会社設立のために要した支出の請求書又は領収書を社長個人名で必ず発行してもらうようにしましょう。
また、社長以外に複数人の発起人がそれぞれ会社設立のために要する支出を行った場合には、同様に個人名で支払先から請求書又は領収書を発行してもらうとともに、支出した個人から支払先発行の請求書又は領収書を添付した立替経費精算書などで会社に請求書を発行してもらい、会社が負担すべき費用であることを明確にしておきましょう。
まとめ
★創立費及び開業費の集計
創立費・開業費にあたるものを理解し、会社名義で支出したもののみならず、会社設立又は開業準備にあたって発起人等個人が立て替えた費用についても漏れなく集計することが必要です。
★会計処理方法
税務上任意償却可能な繰延資産のメリットを生かして節税に生かしましょう。
ただし、任意償却は恣意性が介入しますので、期間損益の適正性などの観点から会計上はあまり望ましくありません。欠損金の繰越控除が全額使えることをシュミレーションしたうえで、支出時に費用処理するか、または定額償却することが望ましいといえます。
★創立費および開業費の評価
繰延資産を資産計上したとしても経過的な貸借対照表科目であるため、各種調査や審査においては資産から除外されます。貸借対照表の評価が必要な場面では、その点に注意しておく必要があります。
関連法規
【会計】
会社計算規則 第74条第3項第5号、第84条
企業会計原則第三 一 D
企業会計原則注解 注15
財務諸表等規則 第36条(繰延資産の範囲)
財務諸表等規則ガイドライン 36
実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
【税務】
法人税法施行令 第14条(繰延資産の範囲)
法人税法施行令 第64条(繰延資産の償却限度額)
法人税法基本通達 8-1-1(定款記載を欠く設立費用)
作成日:2016年11月29日
当コラムは掲載時点での法令等に基づいて記載しておりますが、法令等の改正があった場合にはできる限り追記などの方法で最新の情報に更新しております。
具体的な会計処理や税務処理を行う場合には、最新の法令等を確認されること及び業種や業態、取引内容によっては必ずしも当てはまらない場合がありますので、専門家等に相談されることをお勧めします。
また、当コラムの意見にわたる部分については、筆者の私見であることをお断りします。