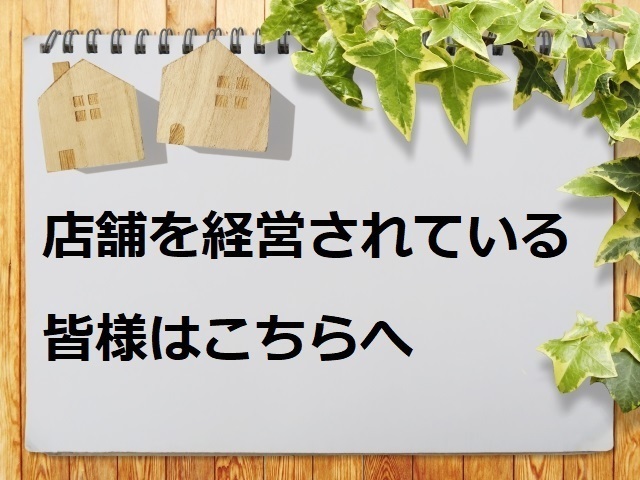東京都港区南麻布 藤岡公認会計士事務所・藤岡正光税理士事務所 中小企業の経営者を支える会計事務所
東京都港区白金3丁目5番11−202号cyuu
営業時間:9:00~18:00(土、日、祝祭日を除く)
減価償却の基本
固定資産を取得した場合、取得後の会計処理として減価償却というものがあります。減価償却は固定資産の種類や金額に応じて様々な処理方法があります。減価償却については、法規が多岐にわたり、どの処理方法をとってよいのかわからないケースがありますので、基本事項について整理します。

減価償却とは
企業会計原則では、「資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。」と規定されています。
つまり、固定資産は1年以上の長期間にわたって使用されるものであるため、固定資産の取得に要した費用を、使用する期間にわたって費用配分する会計処理のことを減価償却といいます。
減価償却に関しては、企業会計原則及び同注解において規定があるものの、個別具体的な会計上の規定はないため、実務上は税法の規定に準拠して、会計処理方法を決定しています。
監査・保証実務委員会実務指針第81号でも、「法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理する場合、不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる(中略)。」とし、不合理でない限り税法の規定に基づく減価償却計算を容認しています。
減価償却方法
一般的に減価償却方法は定額法又は定率法を採用していますが、特殊な業種又は資産に関しては、他の償却方法の採用も認められています。減価償却方法について、企業会計原則注解 注20では、次のとおり定義されています。
【定額法】
固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法
【定率法】
固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
【級数法】
固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した減価償却費を計上する方法
(採用例)顧客関係の無形固定資産(ソフトバンク、新生銀行)
【生産高比例法】
固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法
この方法は、当該固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ、減価が主として固定資産の利用に比例して発生するもの、例えば、鉱業用設備、航空機、自動車等について適用することが認められています。
(採用例)鉱業権(太平洋セメントなど)、鉱業用地(住友金属鉱山など)
【取替法】
同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取替に要する費用を収益的支出として処理する方法(取替法)を採用することができます。
取替法の適用が認められる資産は取替資産と呼ばれ、例えば、軌条、信号機、送電線、需要者用ガス計量器等に適用が認められています。
(採用例)鉄道事業固定資産(JR各社ほか)
耐用年数について
耐用年数には、経済的耐用年数と法定耐用年数の2つがあります。
経済的耐用年数とは、固定資産の種類、構造、用途等のほか、使用環境、同資産の技術革新、経済的事情の変化などの条件から、使用可能と予測した期間を見積もった耐用年数です。
したがって、同じ固定資産であっても使用状況等によって企業ごとに異なる耐用年数となることがあります。
一方、法定耐用年数とは、税法に規定された耐用年数で、減価償却計算の恣意性を排除するために資産の種類、構造、用途別に定められたものです。
会計上は、各企業ごとに、取得した資産の経済的耐用年数を見積もり減価償却計算をすべきですが、実務上、すべての固定資産の経済的耐用年数を見積もることは困難であるため、ほとんどの企業は法定耐用年数を採用しているのが実態です。
税務上の取扱い
税法に規定されている減価償却資産の減価償却方法は、次のとおりとなっています。
資産の種類 | 減価償却方法 |
建物 | 定額法 |
建物附属設備、構築物 | 定額法※ |
機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具及び器具備品 | 定額法又は定率法 |
鉱業用減価償却資産 | 定額法、定率法又は生産高比例法 |
無形固定資産及び生物 | 定額法 |
鉱業権 | 定額法又は生産高比例法 |
リース資産 | リース期間定額法 |
※ 平成28年度税制改正を参照
なお、減価償却を法定の方法以外で行うことについて、税務署長の承認を受けた場合は、その償却方法を選定することができます。
また、減価償却費については、税法上の規定による減価償却方法及び耐用年数に基づく償却限度額内であれば損金算入できることとされており、その償却額は必ずしも償却限度額とする必要はありません。
すなわち、償却限度額と同額を費用処理することもゼロとすることも可能となっています。これが任意償却を利用して利益調整をすることで節税が可能といわれるゆえんです。
平成28年度税制改正
平成28年度税制改正では、財源確保のための課税ベースの拡大をしつつ、法人税率の引き下げが行われていますが、課税ベースの拡大施策の一つとして、減価償却方法の見直しが行われました。
従来、建物附属設備及び構築物の法定の減価償却方法は、定額法又は定率法とされていましたが、平成28年度税制改正で、平成28年4月1日以後に取得等をする建物附属設備及び構築物は定額法に統一されました。
定率法が選択可能な減価償却資産のうち、建物と一体的に整備される建物附属設備及び建物同様長期安定的に使用される構築物については、建物と同様の償却方法に統一したものです。
実務上の留意点
減価償却方法については、資産の区分ごとに選定し、設立の日、その他必要に応じて提出すべき日の属する事業年度に係る確定申告期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を忘れずに提出しましょう。
なお、届出書を提出していない場合は、法定償却方法によることとなります。
まとめ
★耐用年数について
耐用年数には、法定耐用年数と経済的耐用年数の2種類があることを記載しましたが、実務上はほとんどの企業が法定耐用年数を適用して減価償却計算を行っています。
期間損益計算を適切に行う、あるいは投資回収を適切に把握するという観点からは、煩雑であっても経済的耐用年数を適用すべきですし、原則として日本の会計基準及びIFRSでも同様の立場をとっています。特に技術革新が早い現代においては、例えば機械装置など資産の種類によっては、法定耐用年数と経済的耐用年数に大きな乖離が生じる可能性があります。
★減価償却の任意償却
減価償却計算については、税法上はその償却額を償却限度額内で恣意的に決定することができます。すなわち、課税所得の水準に応じて、減価償却額を任意に決めることで、利益調整及び節税ができることとなります。
しかし、この任意償却は期間損益計算を歪めることとこととなり、適切な会計処理とは言えません。上場会社は当然ながら恣意的な減価償却計算である任意償却は認められませんし、金融機関の融資審査では任意償却について考慮したうえで評価を行っています。企業としても業績を適切に反映していないこととなりますので、任意償却は極力避けるべきです。
関連法規
【会計】
会社計算規則 第5条第2項
企業会計原則第三 五
企業会計原則注解 注20
監査・保証実務委員会実務指針第81号 減価償却に関する当面の監査上の取扱い
実務対応報告第32号 平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い
【税務】
法人税法施行令 第5目(減価償却資産の減価償却の方法)第48条から第53条
法人税法基本通達 第7章(減価償却資産の償却等)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
作成日:2016年11月30日
当コラムは掲載時点での法令等に基づいて記載しておりますが、法令等の改正があった場合にはできる限り追記などの方法で最新の情報に更新しております。
具体的な会計処理や税務処理を行う場合には、最新の法令等を確認されること及び業種や業態、取引内容によっては必ずしも当てはまらない場合がありますので、専門家等に相談されることをお勧めします。
また、当コラムの意見にわたる部分については、筆者の私見であることをお断りします。